階段昇降用重量物運搬器具 |
| 田中 矩重(㈲ピアノ梱包/代表取締役) |
|
|
|
重量物を積載して階段を昇降できる運搬機は少なく、国内でも2〜3社しか製造していない。カタログ等で調査・検討を行った結果、アパートやビルの屋内で使用できるものは皆無に等しいことがわかった。学校や展示会場など大きな建物で使用できる大変機能性の高いUSA製品(ピアノプラン)があるが、背丈の大きい自国の建築物に合わせ製作されたもので、階段・踊り場・壁・天井等全ての寸法が小さい日本の住居に使用できる度合いは極めて少ない。特許出願の検索でも上記会社の改良等が多く、小型で屋内で使用可能な機種は見あたらないのが現状であった。 本研究では、らせん階段で生ずる傾斜・階段傾斜・踊り場の方向転回時等に生ずる積載物の安定を保持できる運搬器具の開発を目指し研究を行った。 |
|
|
|
|
以下の項目をキイ・ファクターとして試作を行った。 ①既成の製品は全てゴムクローラで推進しているので同じ方法を用いたい。 ②機体の積載台を二重にし、前後にスライドさせ階段の斜角に応じ荷の重心を変化させたい。 ③狭い踊り場の中で機体を少しづつ回転、進行を繰り返す構造の工夫をしたい。 ④機体を小型化し日本の建築物の屋内で使用可能(1500mm×400mm×250mm以内)にしたい。 その結果、以下の問題が生じた。 ①ゴムクローラは突起ゴムが一定の間隔に配列しているので、寸法の異なる階段では対応できないことがわかった(高さ=17cm〜23cm、奥行=25cm〜35cmなので高さや奥行きが1cm変わるごとに2cm弱の寸法が変わる)。 ②積載台を前後にスライドさせると機体の全長が大きくなり、狭い階段や踊り場ではよけいに不利になる。 ③直進階段を進行し踊り場に達した後に人力で機体を積載物ごと少し浮上させ、機体の低部に備えた自在車を立脚させて人力で少しづつ進行と回転を繰り返すことは可能になったが、狭い踊り場から次の階段に移動するには40cm程機体を(積載物ごと)浮上させなければ回転させられない。 ④機体の小型化は希望どおりに製作することができた。 上記は、試作品を試運転して生じた問題である。 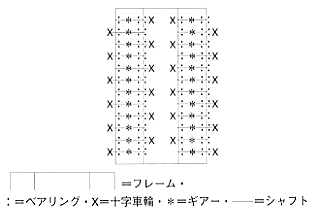
|
|
|
|
|
①ゴムクローラも多くの規格品があると思われるが、本機に希望する規格品を入手することが 困難であり、他の方法を工夫考案しこれを用いて機体を推進させることにした。 A. L型アングルを4片組み合わせ中央にシャフトを貫通するように形成した十字クロス形を作り、これにシャフト・ギヤー・チェーン・ベアリング等を用いて回転を可能にしたもの(以下十字車輪と記す)。 B. 長方形のフレームの左右をそれぞれ2列に形成し(下図参照)、ベアリングを埋め込みシャフトの中程にギヤを備えたシャフトを2列のフレームに貫通させ十字車輪が内側と外側に交互になるように配列し、チェーンを用いてギヤーを連動させて機体を推進させるようにした。 ②荷台を前後にスライドさせると機体の平面積が大きくなり狭い階段をもっと狭くすることになるので、二重構造にした荷台の前部を可動式に固定し後部のみを浮上するように改良し、階段の斜度に応じて積載物を平行に近く保つことができるようにした。 ③踊り場に達した機体が次の段に向かい階段内に安定するまで40cm以上機体を浮上させなければ回転しきれない。前記②の改良で積載物の後部のみ20cm程浮上させることができるようになったがまだ不十分である。 ④機体の小型化は外観では完成したが、鉄製のパイプやアングルを使用したので重量がある。機体内部の空間が小さいので素材を換えて軽量化したい。 |
|
|
|
|
①十字車輪の使用により、階段を捕らえる度合いがゴムクローラの使用時よりスリップしなくなった。しかし、金属なので重量が増してしまった。今後は双方の特徴を併用し、生かせることを工夫したい。 ②荷台の後部のみを浮上することができたが、浮上も沈下もまだ不安があるので改善したい。 ③積載台をさらに浮上させる工夫とともに、機体の低部一点に支点を作り機体を40cm以上浮上できる工夫をしたい。 ④機体全体の軽量化と機体内部の空間を少しでも広くし、上記①、②、③を駆動する装置を一つでも多く組み込みたい。 |

|